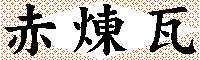 |
2001.9.18 |
|
|
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
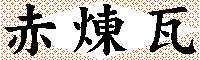 |
2001.9.18 |
|
|
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
|
遠山プランの具体化案示される |
| 8月30日、遠山プランの具体化として、「国立大学の再編・統合を考える際の論点メモ」、「世界最高水準の大学づくりプログラムの骨格」が、第1回大学改革連絡会議(中央教育審議会大学分科会と科学技術・学術審議会学術分科会との合同協議機関)の場で示されました。私たちにとってきわめて重大な内容の文章であることから、若干のコメントとともにここに紹介します。 ①「国立大学の再編統合を考える際の論点メモ」においては、「法人化とも関連して、地方公共団体や学校法人との連携も検討課題」と、国立大学の自治体移管ならびに民営化が示唆されています。また、「文部科学省として具体的な再編・統合計画を策定」と明言されている点も重大です。 ②「世界最高水準の大学づくりプログラム」は、トップ30大学重点化の具体的実施方法の骨格を示したものです。今年度中に実施方法を煮詰め、来年1月には、公募要項を各大学に提示、7月以降に審査、選考するとしています。 資料に示される通り、「全体計画」によると、総額422億円を10分野のそれぞれ30専攻に重点配分。5年間の継続配分としていますが、2年目の中間評価による見直し、入れ替えが示唆されているのです。つまり実際には、1年目で成果を出すことが要求されているのです。これでは長期的視点にたった研究や基礎研究がないがしろにされる危険があります。 また「評価の視点」で示されている評価指標は、数値化された形式的なもの、あるいは政策誘導的なものになっています。これでは数的評価の自己目的化が進行し、政策誘導的業績競争が過熱化していきかねません。また「任期制の導入」を指標としてあげている点は、そもそもの「任期制法」の主旨に反し、文部科学省の意図通りには進まない「任期制」を資金配分によって強制使用とするものであり、断じて容認することはできません。 ではトップ30に入れなかった大学はどうなるか。最後の※に「選定された専攻には、国立学校特別会計や私学助成など、既存の予算も活用して支援を強化」とあります。つまり重点化のために既存予算は削減されるということです。トップ30大学構想は、文部科学省の意図にそって成果をあげた大学を生き残らせ、それ以外の大学をスクラップ化しようとするものだと言わざるをえません。国公私すべての大学を、政府の意図にそって、がけっぷちで競わせようとする政策は果たして誠の学問研究の発展につながるのでしょうか。私たち大学人の責任として、国民とともに遠山プラン反対の声をあげる必要性がいよいよ高まっています |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①国立大学の再編・統合を考える際の論点メモ(案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.再編・統合を進める理由 ・人材大国・科学技術創造立国を目指す上で、国立大学が国際競争力のある大学として活性化、各国立大学の将来の発展のための教育研究基盤の強化 ・大学の構造改革の推進と国立大学法人化等を踏まえた国立大学の教育研究の充実発展 2.統合・再編を検討する際の視点の例 ①教育研究の幅の広がりや体制整備 ②専門教育・学術研究分野の拡大およびそれに触発された新分野の開発 ③地理的近接性 ④人材養成(教員等)への対応 ⑤スケール・メリットの確保(共通の教育研究組織、事務部門の簡素・合理化等) ⑥地域の発展への貢献 ⑦その他 ・法人化とも関連して、地方公共団体や学校法人との連携も検討課題 3.統合・再編の進め方 ・教育研究を直接担う各国立大学が幅広い観点から大胆勝つ柔軟に検討することが必要 ・各国立大学の自主的改革努力を支援 ・これらを踏まえ、文部科学省として、具体的な再編・統合の計画を策定 ・具体的な再編・統合は、一律にではなく段階的に推進 ・構造改革全体の動きに対応した迅速さも必要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②「世界最高水準の大学づくりプログラム」の骨格(たたき台) (案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.全体計画 ・学問分野を10分野に分け、第1フェイズとして、2年計画で10分野をカバー。 ・初年度は5分野を対象とし、各分野30専攻程度を選定。 ・2年間で10分野300専攻程度を選定。 ・対象期間には、5年間継続して経費を配分。 (2年目に中間評価を行い、一部入替え。6年目入替え。) ・第2フェイズでは、分野の拡大(見直し)や経費の充実を検討。 [イメージ]
[積算]
2.分野構成 ・人文、社会科学から自然科学までの学問分野を下記の10分野に構成。 ・分野をまたがるものについても適切な配慮 ・申請に当たっては、各大学がどの分野での審査を希望するかを申告。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.評価の視点(1)教育研究活動実績についての客観的な評価指標として考えられるもの
(2)申請大学からの将来構想及びその実現のための計画(本経費の措置により、どのように世界最高水準の成果を目指すのか等)について審査委員により評価。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経費の使途 評価に基づいて選定された選考等に、当該組織の計画に基づき、必要な教育研究費や人権費、設備費などを重点的に措置(年度あたり1〜5億円程度)。 使途として考えられるものは、例えば次のとおり。・
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||