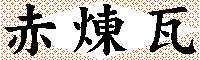 |
2002.1.21 |
|
|
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
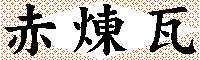 |
2002.1.21 |
|
|
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
|
こばと保育園レセプション |
1月26日11時〜 於・楷樹会館 待ちに待った30周年記念レセプション 昨年7月、30周年記念事業実行委員会を看護部、運営委員会、組合の三者で発足しました。これまで5回の実行委員会をもち、さまざまな記念行事(講演会、クリスマス会など)を行ってきました。なかでもオリジナルTシャツやカレンダーはとてもすてきにできあがりました。 1月26日には楷樹会館において記念レセプションを開催します。 こばと保育園誕生のころ 1970(S45)年、子育てしながら働き続けたいという、母親の切実な願いから誕生したこばと保育園は附属病院の中にあります。設立当初(S41)、保育所をつくる準備会を発足し、まず、それぞれのこどもたちが、現在どのような状況におかれているかを出し合いました。それから小児科医を交えて話し合い、婦長を、すでに職場保育所をつくった経験のある看護婦をと、話し合いの回数を重ね、そのことを「保育所づくりニュース」として発行し、広く理解を深めています。 その後、全職員を対象にしてとったアンケートの結果、93%の人が保育所設置に賛成、90名の園児が入所希望、その内30名が即入所希望という結果が出て、保育所設置が強く望まれていることが再認識されたと、当時のニュースに記されています。 そのような中で、保育所づくりを組合の運動方針として取り上げてもらい、事務部長交渉、病院長交渉、学長交渉を重ね、全国的な看護婦の増員闘争の盛り上がりの中で、1970年(S45)4月1日に「仮設の保育所」が出来ました。こどもを抱えて困っているお母さんたちが、こどもを連れて組合と共に玉井病院長(当時)と直接交渉を行い、倉庫を改装したものではありましたが、園児9名と保母2名でスタートしています。1974(S49)年には現在の場所に建物が新設され、「看護婦授乳室」という名目ではありますが、保育所として運営しても良い、という了解のもとに、こちらの希望する条件とは後退するものの、本格的な保育活動が始まりました。 園児減少の危機をのりこえて 平成6〜7年頃はもっとも園児が減少し、存続の不安を持った時期でした。この時期、鹿大の保育所がなくなり、長大は看護婦のみの数人の利用という状況にあって、何とかしなければという必死な取り組みが存続の危機をのりこえています。 この30周年記念事業の実行委員会を発足するにあたって、昨年の3月にOBを囲んで準備会を持ち、30年をふりかえりました。当時、運営委員長で、組合の四役でもあった安川さんは、当時のことを振り返って次のように語られました。 まず、園舎の老朽化に驚いた。屋根はさび付き、床はささくれ立ち、塀は木製。園児は少なく運営困難な状況にどうしたらよいのだろうかと、途方にくれた。20周年の記念誌を読んで、園の誕生のいきさつや、独自の運営方法をとっていることを知り、初めて園の歴史を知り、理解できた。当局に予算増額を要求しても、らちがあかない。他大学と情報交換してみると、保育所に当てる予算はどの大学とも一致していることなどが判った。単独でやれる状況ではないこと。大学としてやれることは、小さい要求を獲得してゆくしかない。 一方で全国的な大きな運動としての取り組みが必要であると確信し、当局へ、プールをかってもらいたい、出来なければ塀をなんとかして、床を怪我のないように改善して、と丁寧に取り組む中で、要求が1つ1つ実現してゆきました。自分たちで出来ることは積極的に行い、父母でペンキ塗りもしました。このような取り組みが、園の存在を多くの人達に知らせることとなり、次第に入園児もふえ、利用職種も広がってゆきました。 30周年記念誌を作成!! |