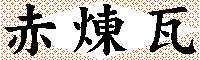 |
2002.3.25 |
|
|
FAX:096-346-1247 E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
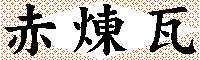 |
2002.3.25 |
|
|
FAX:096-346-1247 E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
|
--病棟婦の大幅削減問題-- |
熊大当局のいまひとつの公約--医療事故防止の観点から「病棟婦の削減を見直しする」 熊大当局は、医療事故の防止という最も重要な視点を欠落させたまま、「合理化の体制が必要だ」として、病棟婦の削減を強行しました。そのため、熊大当局は、病棟婦の削減について「医療事故の事実関係を調査する必要はある」、医療事故防止の観点から「病棟婦の削減を見直しする」と公約せざるをえませんでした(01年3月7日病院長交渉)。 「リスクの高い時間帯における適切な人員配置」 厚生労働省「医療安全対策会議」は、3月18日報告書案(「医療安全推進総合戦略について」)を公表しました。報告書案は、医療機関、医薬品・医療用具メーカー、患者などに対し、それぞれが医療事故対策について果たすべき責務と取り組むべき課題を提示しています。医療機関に対しては、(1)安全管理の理念・指針の作成、(2)安全管理委員会の設置、(3)患者相談の窓口の設置、(4)「リスクの高い部門、リスクの高い時間帯」における手厚い人員配置、(5)教育研修、(6)業務手順の標準化、(7)事故の報告体制の整備、などを求めています。 横浜市立大の医療事故以降、また医療法施行規則の改正(00年4月)以降、熊大病院も医療事故防止策に取り組んでおり、報告書案が医療機関に求めた対策の7つのうち6つに取り組んでいます。しかし、報告書案が「特に、医療機関におけるリスクの高い分野については、優先的に〔安全対策に〕取り組む必要がある」と指摘しているにもかかわらず、熊大当局は「リスクの高い部門、リスクの高い時間帯」における手厚い人員配置に取り組むどころか、全く逆に、事故が発生しやすい勤務帯・時間帯の人員を大幅に削減しています(病棟婦の大幅削減)。 与薬事抜が発生しやすい時間帯 日本病院会「医療事故の対策に関する活動状況調査」は、会員病院て過去1年間に発生したアクシデントについて分析し、82.6%のアクシデントに看護婦が関係していることを明らかにしています。川村治子(厚生科研費研究)「看護のヒヤリ・ハット事例の分析」は、「看護のヒヤリリ・ハット事例の44.3%が与薬(経口薬・注射・点滴・IVHなど)で発生していることを明らかにしています。要するに、医療事故のリスクが最も高いのは看護業務であり、なかでも与薬業務が最も危険なのです。 医療安全対策会議報告書案は、病院に「リスクの高い時間帯」があることを指摘していますが、最もリスクの高い与薬業務については、すでにその勤務帯・時間帯が明らかにされています。日本看護協会「誤薬事故に関する調査」(00年11月公表)は、首都圏の11の病院を対象に、「ダブルチェックなど確認の努力がなされているにもかかわらず」発生した、257件の誤薬事故について分析しています(第1図参照)。それによれば、(1)勤務帯別では、日勤帯で全般的に誤薬事故が発生しており、準夜勤帯については「18:00〜20:59」に誤薬事故が集中しています。(2)時間帯別ては、「18:00〜20:59」が19.8%で最も多く、次いで「9:00〜11:59」が16.3%、「12:00〜14:59」が16.0%となっています。実に誤薬事故の52.1%がこれら3つの時間帯(計9時間)に発生しています。
(註)この調査の対象病院の総病床数は7,528床、調査時の平均稼働率は92.5%、対象病院に勤務する看護婦総数は5,397人とされています。つまり、熊大の看護婦配置をはるかに上回る患者1.3に対し看護婦1人の配置がなされていました。 熊大当局は公的を守れ 看護業務は最も医療事故のリスクが高く、とりわけ与薬業務のリスクが高く、わけても日勤帯。食事の時間帯のリスクが高いのです。にもかかわらず、熊大当局が強行した病棟婦(勤務時間7:30〜18:30)の削減によって、日勤帯および最もリスクの高い3つの時間帯の看護婦の業務が増え、煩雑になりました。熊大当局は、一方では、看護婦に早期退職を余儀なくさせつつ、また平均在院日数の短縮によって医療事故のリスクを高めつつ、他方ではこともあろうに、そもそも最もリスクの高い看護業務の、それもきわめてリスクの高い勤務帯・時間帯に、看護婦の業務を増やし煩雑化させたのです。 熊大当局には、(1)「リスクの高い部門、リスクの高い時間帯」における手厚い人員配置を行うつもりがあるのか、ないのか。行うつもりがあるのであれぱ、いつから行うのか。(2)医療事故の防止の観点から「病棟婦の削減を見直しする」つもりがあるのか、ないのか。行うつもりがあるのであれぱ、いつから行うのか。(3)これらを行うつもりがないのであれぱ、「事故が発生しやすい勤務帯・時間帯」に対して、いかなる医療事故防止策をとるのか。−−この3点について、来る学長交渉で明確にお答え願いたい。 |