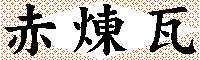 |
2002.4.5 |
|
|
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
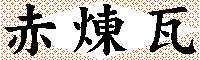 |
2002.4.5 |
|
|
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
|
(最終報告)に対する 反対声明の発表について |
熊本大学教職員組合は、執行委員会で議論した結果、3月26日の夕刻、“声明:「新しい『国立大学法人』像について」(最終報告)の撤回を求める”を発表し、県政記者クラブに送付しました。 この反対声明の公表を契機に、学内論議をさらに深めるとともに、「国立大学法人」法の法案化阻止に向けて、「『大学の構造改革の方針』の見直しと大学・高等教育の充実を求める請願」署名活動に奮起されるよう組合員のみなさんに心より訴えるものです。 声明:「新しい『国立大学法人』像について」(最終報告)の撤回を求める 2002年3月26日 熊本大学教職員組合 3月26日、国立大学の法人化後の運営方法などを検討している文部科学省調査検討会議が、最終報告「新しい『国立大学法人』像について」をとりまとめ、文部科学大臣に提出した。しかしそこに示された制度設計の方向は、私たち教職員の雇用・労働条件を不安定化すると同時に、学問の自由と大学の自主性・自律性を脅かし、その結果、学術研究・高等教育・医療の発展の基盤を崩し、日本の社会、国民に取り返しのつかない深刻な悪影響を及ぼすものであり、断じて容認することはできない。 私たちは、すでに昨年9月に公表された「中間報告」に対して、「声明」を公表し、その中で、「中間報告」に示された制度設計の中身が、「独立行政法人通則法」とほとんど変わるところがないことを指摘し、(1)各大学は、自律性を持つどころか、文部科学省ならびに「国立大学評価委員会」の絶大な権限の下に置かれることになる、(2)大学運営に関する「学外者」の権限が肥大化し、教職員のイニシャチブが奪われ、その結果、真理探求という本来の大学の使命を離れ、政府・財界の要求に沿った大学運営が強引に押し進められる危険がある、(3)学生納付金の大学間・学部間格差の容認は、大学の再編・統合問題と共に、高等教育の機会均等原則を政府自らが踏みにじり、国民・学生にいっそうの多大な負担を強いるものである、(4)任期制の導入など、雇用関係や労働条件の流動化・不安定化がうながされ、そのために教育研究の継承性や安定性が損なわれる可能性がある、などの問題点をあげた。そして、今後、さらなる制度設計の具体化が、「国公私トップ30の育成」ならびに「大胆な再編・統合の推進」とセットで押し進められるならば、国公私すべての大学に対して、国策に沿った形での、生き残りを賭けた忠誠競争が強要されるにちがいないと批判した。 だが、今回の最終報告は、そうした問題点や批判を考慮した形跡はほとんどなく、むしろ以下の点で「中間報告」以上に問題をはらんだものとなっている。 具体的にあげれば、第1に、教職員の身分について、「非公務員型」を採用するとしている点である。これは、「任期制の積極的導入」や「業務のアウトソーシング」の推進と共に、教職員の雇用・身分保障を不安定にし、労働条件の引き下げを容易にするものである。さらには、教育公務員特例法の適用除外によって、学問の自由と大学の自治が破壊され、そのことが日本の大学・高等教育に及ぼす影響は、きわめて深刻で長期的なものとならざるをえない。また、国家公務員は国民全体の奉仕者であるとの考え方から、営利企業との兼業については人事院規則により「当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、且つ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がない(人事院規則14-8、第1条)」場合に限定されている。ところが「最終報告」は「非公務員型」選択の理由の一つとして「営利企業の役員等を含む兼職・兼業について、法人の方針に基づく弾力的な運用」をあげている。大学の教職員がむやみに営利企業の役員等と兼業・兼職することは、国民全体への奉仕者から営利企業への奉仕者となりかねず、公共的性格を持つ大学の使命をないがしろにするものである。 第2に、「運営組織の在り方」について、教学の分離を明確に打ち出している点である。「最終報告」は、経営面に関する運営協議会と教学に関する評議会を分離し、運営協議会には「相当程度の学外の有識者を参画させる」としている。しかし、教学と経営の一体的かつ円滑な意思決定システムは、研究と教育への「不当な支配」を排し、大学の学問研究の自主的・自律的発展を保障する上で絶対に譲れない原則である。また役員や、評議会のメンバーはすべて大学構成員(常勤の職にある者)でなければならず、非常勤の職にあって大学の運営にかかわることのできる機関は、諮問機関としての性格をもつものに限定すべきである。 第3に、学長の選考方法を、教職員の意向や総意よりも、運営協議会に参画する「学外有識者」の意見を重視する仕組みに変えようとしている点も重大である。「最終報告」は、「学長選考委員会(仮称)の判断により、投票参加者の範囲を…教育研究や大学運営に相当の経験と責任を有する者に限定する」とし、教職員の投票範囲を制限する一方、学長の選考基準、選考手続き、選考過程のすべてに「学外」の意見、すなわち運営協議会の学外メンバーの意向を反映させようとしている。本来学長の絶大なリーダーシップは、より広範な教職員の支持があってはじめて可能となるはずである。しかし、このように学長の人事までが、「学外有識者」の意向によって左右されることになれば、大学の学問・研究の発展は大きくゆがめられることになるだろう。 以上のように、調査検討会議の「最終報告」の内容は、断じて受け入れがたいものであり、私たちは文部科学省に対し、その撤回を強く求めるものである。また現在、私たちは「大学の構造改革の方針」の見直しを求める百万人署名に取り組んでいる。引き続き「国立大学法人法」の法案化への動きを阻止するために粘り強い運動を進めると同時に、良識ある大学人として、大学の研究と教育が、人類の福利に寄与し、地域と国民に開かれたものとなるよう今後とも努力する決意である。私たちの取り組みに対して、大学関係者はもとより、広範な国民の支援と協力を心から呼びかける。 |