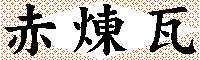 |
2002.5.24 |
|
|
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
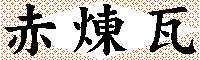 |
2002.5.24 |
|
|
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
|
は最高の看護体制ではありません |
|
問題の本質は、病院長会議でも指摘している『医療の密度』の加速度的上昇への対応の遅れ!! 「赤煉瓦」No.38で取り上げた問題について、4月9日熊大当局から次の回答がありました。(1)「"2対1以上のことはありえない"、"2対1は最高の看護体制であり、それ以上は望めない”という回答は、例えば患者1.5人に対し看護婦1人を配置しても、診療報酬を請求する際には2対1が最高のものという主旨である」。(2)「夜間看護加算について、病棟に1.5対1の看護婦を配置し、10対1の夜勤看護加算を算定するためには、看護要員の大幅な増員が必要になる。100人の増員が必要であり人件費が4億円必要となる。他方、10対1の夜勤看護加算を算定しても見込める増収額は6,000万円程度である。投資の割には増収が少ないということで会計検査院から怒られる可能性がある。会計検査院の指導は、無駄かどうか適正に執行されているかどうかを見る。取れる金を取らなかった、あるいは基準以上の投資をした場合など指摘される。」成り立たない計算 熊大当局はこの回答においても入院基本科・診療報酬の仕組みを理解していません。そのことは、10対1夜勤看護加算を算定した場合の増収見込額を約6,000万円とする回答に端的に現れています。この計算式は、1日あたり患者数×診療報酬の点数(1点=10円)×365(日)です。
実は、この計算式はひとつの前提のもとでのみ成り立つ計算式です。在院日数が一定であるという前提です。しかし実際には、熊大病院の平均在院日数は96年度の42.3日から、01年4〜11月の29.0日へと大幅に短縮されています。平均在院日数の短縮とは、患者の回転率が上昇することに他なりません。平均在院日数の短縮にともなって、新入院=退院患者数が増加します。熊大病院では96年度から01年4〜11月の間に、退院患者数が47.1%も増加しました(第1表参照)。こうした状況下では上記のような単純な計算によっては、増収見込額を正しく算出することは決してできません。 というのも、「1日あたり患者数」は、患者の回転(新入院=退院患者数)を表現しないからです。平均在院日数がどんなに短縮されても(新入院=退院患者数がどんなに増加しても)、「1日あたり患者数」は変化しないことがありえます。実際、97年度以降熊大病院の「1日あたり患者数」はほとんど変化していません。つまり、97年度以降熊大病院では「1日あたり患者数」に変化がなくても、新入院=退院患者数の激増という変化が起こっています。「1日あたり患者数」を根拠とする上記の単純な計算式によっては、新入院=退院患者数の激増にともなう病院収入の変化を計算することはできません。 診療報酬・入院基本料の仕組み しかし、入院基本料は平均在院日数の短縮(新入院=退院患者数の増加)を評価しています。それが「赤煉瓦」No.38で述べた、出来高払いの仕組みです。上記の回答・計算においても熊大当局は出来高払い制を無視していますので、再度説明しておきます。入院基本料の出来高払い制とは、「入院期間」に応じた加算・減算の仕組みのことです。「入院期間」が「14日以内」および「15〜30日以内」の場合には「基本点数」に加算がなされます(「初期加算」)。とりわけ「14日以内」に高い加点が設定されています。
在院日数の短縮(≒入院期間の短縮)によって、「初期加算」の算定による増収が実現するだけではありません。在院日数の短縮にともなって新入院=退院患者数が増加するため、それとともに検査件数、投薬・注射件数および手術件数が増加します。当然これらの診療報酬が増額となりますが、上記の単純な計算はこうした増収額も表現していません。要するに、熊大当局が持ち出してきた計算は、二重の意味で、在院日数の短縮(新入院=退院患者数の激増)にともなう病院収入の変化を表現していません。 問題の本質 熊大当局は、一方において在院日数を大幅に短縮し、それによって新入院=退院患者数を大幅に増加させつつ、他方において在院日数の不変を前提とした計算によって、人員が増やせないという結論を導き出しているわけです。「やっていること(在院日数の大幅な短縮)」と「言っていること(在院日数が不変)」が全く違うのです。 熊大当局は今回もまた「会計検査院から怒られる」などと回答していますが、本質的な問題は、熊大当局が、一方において在院日数を大幅に短縮させつつ、それによって新入院=退院患者数を大幅に増加させつつも、他方において大幅に増加した患者への対応に本来必要な人員増を全く怠っている−−換言すれば増員の見通し・方針を立てられない−−ことにあります。熊大病院では96年度から01年4〜11月の間に、退院患者数が47.1%も増加していますが、この期間に熊大当局は看護要員をわずかに16人(3.3%)増員したにすぎません(第1表参照)。熊大当局はこの怠慢を隠蔽するために、怠慢を言い逃れるために、会計検査院という威を借りようとしているにすぎません。それもご都合主義的に。というのは、退院患者数の増加にともなってサービス残業が拡大しました(「赤煉瓦」No.40)が、この場合に熊大当局は頼みの会計検査院を担ぎ出せない−−超勤手当を適切に執行していない−−ので、「なぜ超勤が増えたのか分からない」などと白を切ります。 国立大学医学部附属病院長会議の提言 国立大学医学部附属病院長会議「医療事故防止のための安全管理体制の確立に向けて(提言)」(01年6月)は、熊大当局よりも真摯に(したがって正しく)事態を把握しています。「国立大学病院においては、集中的な全身管理を要する『高額医療』をはじめとして、大きな手術や高度な検査の件数が増加の一途をたどっているが、また一方では、この数年来、新たな入院患者の数も顕著に増加してきており、在院日数の短縮化と相まって、『医療の密度』が加速度的に上昇する傾向にある。これらの指標からも、全体として、診療活動の業務量は急速に増大してきていると言えるだろう」(p.31)。(註)「提言」本文には「これらの指標」(新入院患者数や検査・手術件数などの増加)が図示されています(pp.57-8)が、本紙では紙幅の関係上割愛せざるをえません。 ここでは、「在院日数の短縮化」によって、「新たな入院患者(新入院=退院患者数)」が増え、それとともに「大きな手術や高度な検査の件数」が増えたため、「医療の密度」が、したがって「診療活動の業務量」が増大したと把握されています。熊大当局とは異なり事態が正しく把握されています。 事態が正しく把握されれば、おのずと正しい対応策が導き出されます。「マンパワーに応じた適切な病床数の見直しも考慮すべきである」(p.32)と。「適切な病床数の見直し」とは「1日あたり患者数」の削減を意味します。この対応策は、「1日あたり患者数」を維持しつつ、在院日数の短縮(新入院=退院患者数の増加)を進めること−−熊大当局の方針−−を否定し、在院日数の短縮にともなって「1日あたり患者数」を削減するということです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||